「情報資源組織論」2025・2026年設題
指定したキーワードをすべて使って、各設問の解答を完成させてください。
1.現在、多くの公共図書館や大学図書館で、外部の書誌データを利用した目録作成業務が行われています。集中目録作業と分担目録作業(=共同目録作業)、それぞれの特徴(意味や役割、課題など)を明確にし、さらに今後の目録作成業務のあり方について自らの見解をまとめてください。(1,000字)
<キーワード:MARC、集中目録作業、分担目録作業、総合目録、書誌ユーティリティ>
2.地域の図書館(公共図書館)での現地調査もしくは調査対象館のHPの蔵書検索により、「蔵書の所在記号(背ラベル)の付与のしかた」について複数ケースを洗い出し、気づいたことをまとめてください。さらに、調査で得た内容や関連情報をもとに、書架分類と書誌分類という二つの点から、NDCの分類(記号)を活用することの意義や課題について考察してください。尚、調査対象館は“NDCを採用する近隣の公共図書館”で、取り扱う情報資源は“紙資料”とします。(1,000字)
<キーワード:書架分類、書誌分類、目録、配架(テキストでは排架を使用)、所在記号>
「情報資源組織論」合格レポート
※レポートの丸写しは禁止されています。あくまでも参考に留めてください。
※特定を避けるために内容を少し修正しています。
設問1
1.はじめに
近年、図書館における目録作業は、機械可読形式の書誌レコード(MARC)をコンピュータ・ネットワークを用いて共有することで行われている。本論では目録作業の方法についてまとめるとともに、今後の目録作成業務の在り方について考察する。
2.目録作業の方法
目録作業の方法として、集中目録作業と分担目録作業がある。
集中目録作業は、一つあるいは少数の図書館等が目録を作成し、他の図書館がその書誌レコードを利活用する方法である。知識や技術をもった作業者が高品質なMARCを作成することが期待できる。一方で、書誌作成作業を行わない図書館では、新刊書の提供にタイム・ラグが生じる点が課題である。また、総合目録が自動的には作成されないため、横断検索やハーベスティングによるデータベースの構築が必要である。
分担目録作業は、多くの図書館が共同で書誌レコードを作成し、利用する方法である。不足する書誌データを自館で作成できるため、タイム・ラグの問題が少ない。また、参加館が所蔵を登録することで、総合目録データベースの役割を果たすことが期待できる。一方で、作業者の水準にばらつきが生じるため質の担保が課題となるほか、参加館の積極性の違いにより作業負担が不均衡になる懸念がある。参加館の実務やシステム等を管理する組織である書誌ユーティリティが必須である。
3.今後の目録作成業務の在り方
今日では情報通信技術の発展により、「国立国会図書館サーチ」のようなハーベスティングによる統合検索や、「カーリル」のような横断検索による総合目録サービスが実現されている。集中目録作業により、品質の高い書誌を迅速に作成し全国で共有することができれば、こういった検索システムによる書誌の同定が確実になり、効果的な情報探索につなげることができるだろう。一方で、オンデマンド出版資料や地域資料など、流通が小規模な資料については、地域の図書館や書誌ユーティリティと連携し、役割を分担することも必要となる。分担目録作業にあたっては、書誌レコードの質を担保するため、目録規則についての認識を作業者間で共有するとともに、機械学習やAIなどの技術を活用し、チェックを行う仕組みを構築することが必要であると思う。
4.おわりに
本論を通じて、効率的かつ良質な目録作成の在り方について考えを深めることができた。図書館員が情報技術の発展を注視し、よりよい在り方を模索していくことが重要であると思う。
参考文献
田窪直規編著ほか『情報資源組織論. 3訂』樹村房,2020.3.
「国立国会図書館サーチ」https://ndlsearch.ndl.go.jp/
「カーリル」https://calil.jp/
設問2
1.はじめに
本論では、●●区立●●図書館における所在記号の付与のしかたについての現地調査を通し、NDCの分類を活用することの意義や課題を考察する。
2.●●図書館における所在記号
同館の所在記号(同館では「請求記号」と呼ぶ)には、以下の三つの類型が見られた。
①NDCの分類記号
所蔵資料の多くについて、主題に応じてNDC細目表の第5次区分までの分類記号を付与している。文学関係など一部の分類では、図書記号として著者名あるいは被伝者名の頭文字を付している。
(例)関口 安義編「芥川龍之介 生誕120年」(翰林書房, 2012)請求記号910.26/ア/
②別置記号+NDCの分類記号
ヤングアダルト資料・地域資料等のコーナーに別置されている資料には、別置記号が付与されている。NDC分類は①の資料より簡素に、第2次区分までを付与しているコーナーもある。
(例)板橋区議会事務局編「板橋区議会年報 令和5年度」(板橋区議会事務局, 2024)請求記号Ki31.4(地域資料)
③所在記号なし(目録上のみの付与)
新書・文庫には背ラベルが貼付されておらず、レーベル別のシリーズ番号順で配架されている。目録上では、別置記号とNDCの第3次区分までの分類記号が請求記号として付与されている。
(例)瀬田 貞二著「幼い子の文学(中公新書563)」(中央公論社,1980)目録上の請求記号S909
3.NDC活用の意義と課題
●●図書館での調査を通じて、書誌分類・書架分類の双方にNDC分類を活用することで、目録の検索とブラウジングを行き来しながら、効果的な資料探索ができるように感じた。たとえば、キーワード等による目録の検索から行き着いた書架でのブラウジングにより、より適切な分類記号を特定し、再度目録を分類記号で検索して、書庫の資料や別置資料を含めて探索することが可能である。
一方で、同館では1書誌に1つのNDC分類しか付与していないため、複数の分類にまたがる資料は見落としが生じやすい。目録上では複数の分類を付与するほか、書架分類では複本がある場合にはそれぞれ異なる分類を付与する、複本がない場合には代本板を入れて誘導するなどの工夫ができるとよいように思った。
4.おわりに
今回の調査を通して、書誌分類でも書架分類でもNDCを活用することは利用者の情報へのアクセスを助けるものであると感じた。利用者がNDC分類の仕組みを理解し、より効果的に利用できるよう、教育にも努めることが重要であると思う。
参考文献
田窪直規編著ほか『情報資源組織論. 3訂』樹村房, 2020.3.
板橋区立図書館「蔵書検索」https://www.lib.city.itabashi.tokyo.jp/licsxp-opac/

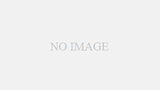
コメント