「図書館情報技術論」2025・2026年 設題
・司書(図書館職員)が図書館の運営に携わる中で、あるいは、利用者が図書館を利用する中で、情報技術が活用されている場面を想定し、その状況を説明してください。その際、活用されている情報技術の名称及びどのような技術なのかについても含めてください。 ・その上で、記述した活用場面において、該当の情報技術を活用することのメリットと考えられるデメリットについて、それぞれ具体的に述べてください。なお、デメリットの記述量はメリットの記述量を超えないよう収めてください。 ・文章の最後に、文中で述べた「活用されている情報技術の名称」を例示の形に倣って挙げておくこと。 例「情報技術の名称: (1) ○○○ (2) △△△ (3) □□□・・・」
「図書館情報技術論」合格レポート
※レポートの丸写しは禁止されています。あくまでも参考に留めてください。
1.はじめに
現代の図書館では、さまざまな情報技術が重要な役割を担っている。本レポートでは、司書や利用者が図書館を運営・利用する中で情報技術が活用されている場面を想定し、活用されている技術を説明しつつ、導入によるメリットとデメリットを論じる。
2.図書館で活用される情報技術
(1)資料の収集・整理
図書館職員が資料の選書、受入、除籍、書誌情報の整備を行う際には、「蔵書管理システム」が活用されている。これは、選書・発注レコード、書誌レコード、所蔵レコードなどを一元的に登録・管理できるシステムである。現在では、後述する貸出・返却システムや予算管理、統計処理などを含めた「統合図書館システム(ILS:Integrated Library System)」として運用されている場合が多い。
このようなシステムの導入により、資料の所蔵管理が効率的に行えるほか、他機関の書誌データを活用して業務を簡略化できる。また、他館との所蔵データの共有により相互貸借の迅速化も図れる。一方で、導入・維持に高額な費用がかかるため、小規模館には大きな負担となる。また、システムの仕様に業務が制限される場合がある。
(2)資料検索
利用者が図書館の蔵書を探す際に利用されるのが、「OPAC(Online Public Access
Catalog)」である。これは、蔵書管理システムと連携し、所蔵情報をWeb上に公開することで、利用者がキーワードや著者名などから資料を検索できるシステムである。スマートフォンや自宅のパソコンからもアクセス可能で、資料の所在や貸出状況が容易に確認できる。
OPACの利点として、アクセスの利便性のほか、直感的な操作で資料検索が可能なこと、検索履歴の保存や類似資料の表示など高度な検索機能がある点が挙げられる。しかし、検索キーワードが正確でないことなどにより、目的の資料がヒットせず、存在しないものと誤認させてしまう可能性がある。また、書架を歩いて思いがけない本と出会うセレンディピティの機会が減少する側面もある。
(3)資料の貸出・返却
利用者が資料を貸出・返却する際には「貸出返却システム」が活用されている。利用者ごとに資料の貸出・返却の情報が即時に反映され、貸出の上限冊数等が管理できるシステムである。近年は「RFID(Radio Frequency Identification)」技術を用いたICタグが資料や利用者カードに組み込
まれ、自動貸出機・返却機によるセルフサービスが一般化している。
この技術の導入により、職員の貸出・返却業務の負担が軽減され、手作業によるミスも減少する。利用者側にとっても、OPACを通じた予約や延長申込みが可能となるなどの利点がある。ただし、RFID機器やICタグの導入・保守には高額な費用がかかる。また、読み取り精度の問題や個人情報保護に関する懸念も残されている。
(4)電子資料の提供・利用
近年、多くの図書館で「電子書籍配信システム」や「商用データベース」、「デジタルアーカイブシステム」等を導入しており、利用者は図書館の内外で電子資料にアクセスできる。また、「リンクリゾルバ」という技術を活用することで、OPACから電子資料も含めた適切な情報へのアクセスが可能となる。さらに、大学図書館では、研究成果を蓄積・公開する「学術機関リポジトリ」の整備が進んでいる。
これらの電子資料の利点として、スペースの節約に加え、全文検索や引用リンクの活用など、高度な情報検索が可能となる点がある。一方、商用データベースの契約費用やデジタルアーカイブシステムの保守運用費用などが高額となり、継続的な利用が困難となる可能性がある。
(5)レファレンスサービス
図書館ではWebフォーム、メール、チャットを通じた質問受付を行うデジタルレファレンスサービスを実施する図書館もある。一部の図書館では、「AIチャットボット」による自動応答型レファレンスサービスの試行も始まっている。
これらのサービスは、時間や場所を問わず利用者が質問できる点で利便性が高く、質問のハードルを下げる役割を果たしている。また、過去の質問事例を蓄積・共有できる点もメリットである。しかし、利用者の意図を深く掘り下げるのが難しく、複雑な調査には限界がある場合も多い。AIチャットボットの回答の精度の問題もある。
3.おわりに
図書館における情報技術の導入は、資料管理や利用者サービスの向上に大きく貢献している。一方で、その導入には予算や人材、技術面での課題も多く、小規模館では対応が難しい場合も少なくない。図書館間の連携やクラウドサービスの活用を進め、情報格差を是正し、持続可能な情報サービスの提供体制を整える必要があると思う。
情報技術の名称:(1)蔵書管理システム、(2)統合図書館システム(ILS)、(3)OPAC、(4)貸出返却システム、(5)RFID、ICタグ、(6)電子書籍配信システム、(7)商用データベース、(8)リンクリゾルバ、(9)学術機関リポジトリ、(10)AIチャットボット
参考文献
・日高昇治著『図書館情報技術論. 第3版(ライブラリー図書館情報学3)』学文社, 2022.12.
・塩崎亮, 今井福司, 河島茂生編著『図書館情報技術論: 図書館を駆動する情報装置. 第2版(講座図書館情報学4)』ミネルヴァ書房, 2022.5.

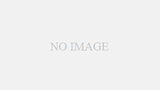
コメント