「生涯学習概論」2025/2026年 設題
設問1 生涯学習の方法や生涯学習の支援方法について述べるとともに、それらの法的根拠も詳しく述べなさい。
設問2 生涯学習振興行政における行政改革の推進や、社会教育行政の新たな展開について述べなさい。
「生涯学習概論」合格レポート
※レポートの丸写しは禁止されています。あくまでも参考に留めてください。
【設問1】
生涯学習の方法には、大きく分けて「個人学習」と「集合学習」がある。
個人学習とは、学習者が自らの興味や目的に応じて自主的に行う学びの形態であり、読書、個人指導による習い事、通信教育、観劇・鑑賞、インターネットを活用したeラーニングなどが含まれる。学習内容や方法を自ら選択できる点が特徴であり、生涯学習の中核とされる。一方で、学習の継続やモチベーションの維持が課題となることも多い。
これに対して、集合学習は複数の人々が同じ場所に集まり、相互に関わり合いながら学ぶ方法である。講演会や展覧会などの「集会学習」と、講座や教室における「集団学習」があり、後者では学習者間の交流を通じて学びを深められる点が特徴である。制度的な教育機関による学習に加え、「ノンフォーマル教育」と呼ばれる意図的かつ組織的に行われる学習活動も含まれる。ノンフォーマル教育の例として、自治体の市民講座、NPOのワークショップ、図書館・博物館での体験学習などがあり、学歴や年齢に関わらず誰もが参加できる。これにより、学習者の主体性が育まれ、地域における社会的つながりの強化にも寄与する。
こうした生涯学習を支援するため、自治体による生涯学習センターの設置、公民館・図書館・博物館の運営、学習相談体制の整備など、地域に根ざした支援が展開されている。また、大学、NPO、民間企業やボランティア団体等、様々な機関と連携することで、より専門性が高い講座や、親しみやすい学習機会が提供されている。
これらの支援には法的根拠がある。戦後すぐの1947年に制定された教育基本法では、社会教育が「奨励されなければならない」と規定され、これを受けて社会教育法、図書館法、博物館法が制定され、公民館、図書館、博物館等の社会教育施設の運営と役割が制度的に位置づけられた。さらに1990年には「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」が制定され、「生涯学習」という法的概念が初めて明文化された。この法律に基づき、多くの都道府県や市町村に生涯学習センターが設置され、地域住民の多様な学びの場が提供されている。
2006年には教育基本法が改正され、第3条に「国民一人一人が…その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」と明記された。これにより、生涯学習は、国民の権利であり、社会全体で保障すべきものとして位置づけられた。
【設問2】
2000年に「行政改革大綱」が閣議決定されて以降、生涯学習振興行政および社会教育行政においても、効率的かつ柔軟な行政運営を目指した改革が進められてきた。その一つが、社会教育施設への独立行政法人制度の導入である。これまで国が直轄していた国立科学博物館や国立少年自然の家、国立婦人教育会館などは独立行政法人化され、施設ごとの自立した運営と経営的視点に基づく管理が求められるようになった。
自治体においても、2003年の地方自治法改正により導入された指定管理者制度により、公民館や図書館、博物館といった社会教育施設の管理運営を、民間企業やNPO法人などの外部団体に委託できるようになった。これにより、運営の効率化やサービスの多様化が進んだ反面、委託契約の更新制によるサービスの継続性の確保や、専門職員の育成・定着が課題となっている。
2006年の教育基本法改正を受けて、2008年には社会教育法、図書館法、博物館法が改正された。これらの法改正では、社会教育行政が生涯学習の振興に寄与するために、学校・家庭・地域住民などの関係者が相互に連携・協力する体制づくりが強調された。とりわけ学校との連携強化が重要な政策課題として位置づけられている。
また、同年の中央教育審議会においては「知の循環型社会」の構築が提唱された。これは、大学や研究機関、地域社会、企業などが連携し、知識や経験を社会全体で循環させることで、学習力と創造力の向上を図るものである。この理念の下、地域連携型の生涯学習プログラムや大学による公開講座、社会人向けのリカレント教育など、多様な学習機会が創出されている。
さらに、2009年以降に行われた「事業仕分け」では、限られた財源を有効に活用する観点から、生涯学習関連施設の必要性や事業の効果が厳しく問われた。これに伴い、事業成果を客観的に評価・公表する仕組みづくりが進められている。
現在も文部科学省を中心に各省庁で生涯学習支援の取組みが続けられているが、社会保障費の増大などを背景に、社会教育行政の財政状況は一層厳しさを増している。そのような状況下で注目されているのが「新しい公共」の考え方である。これは、公共の担い手を行政だけにとどめず、市民・NPO・企業・大学など多様な主体に広げ、地域課題の解決や公共サービスの提供を社会全体で担おうとする理念である。生涯学習の領域においても、地域社会の一人ひとりが主体となって学びを支え、共に学ぶ場を協働して創り出していくことが求められている。
参考文献
・浅井経子編著『生涯学習概論 : 生涯学習社会の展望. 新版』理想社, 2019.10.

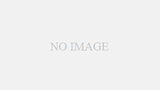
コメント